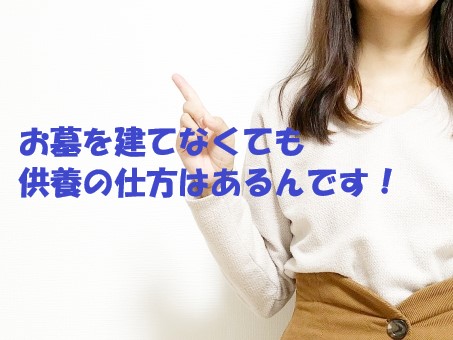
さまざまな方法はあるようですが、今回は遺骨を自宅で保管する方法について説明したいと思います
遺骨を自分で保管する

墓地以外のところに「埋蔵」すると違反になってしまいますが、「保管」つまり、埋蔵そのものをしなければ違反にはなりません。埋蔵せずに供養ができるもっとも簡単な方法として自分で保管するということになります。よくお仏壇の中に骨壷を置いてあるのを見かけることがありますが、法律では、遺骨を墓地に埋蔵しなくてはいけない期限も特に定められているわけではないようです
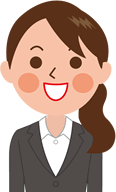

「手元供養」
故人を身近に感じて、手を合わせて祈る。残された家族の離れがたい気持ちを形にするものが手元供養です。
手元供養をするためにはどうしたらいいですか?
方法
お骨を入れて身に付けることができる「遺骨ペンダント」や分骨して手元に置くことが出来る「ミニ骨壷」などにお骨を手元に残して供養することができます
手元供養はこのような方におすすめです
- ご遺骨を身近においておきたい方
- 定期的なお墓参りが困難な方
- 何らかの事情でお墓を建てられない方
- 常に故人を身近に感じていたい方
- 様式に縛られないお参りをしたい

それらは俗説です。お釈迦様自身は御自身のお骨を分骨しお祀りされているようです。故人の魂はご遺骨に宿るものでしょうか?仏教でも49日を過ぎれば仏様になるといわれています。個人のご遺骨を自宅で保管することは法律では問題ないので大丈夫です。
手元供養の残りの遺骨はどうする?
手元供養でおさめるご遺骨はほんの少量になります。では、残りのご遺骨はどうすればいいのでしょう?
手元供養で遺骨が残る
すべてのご遺骨を残す場合もありますが、一般的にはご遺骨を分骨し、一部だけを手元供養用として残します。手元供養では、ペンダントをはじめとする遺骨アクセサリーや小さな骨壷にご遺骨を納めますが、ごく少量のご遺骨を納めるだけなので大半のご遺骨は残ってしまいます。お墓を持たないときは、残った遺骨をどうしたらよいのか悩んでしまう方もいるのでは?
手元供養で残るご遺骨の行き先
合祀永代供養
”合祀永代供養墓”という共同のお墓に残りのご遺骨を納めることができます。お墓が「合同墓」「合葬墓」「共同墓」などと呼ばれるように複数の方のご遺骨と一緒に納められます。お墓の無縁化の急増にともない、自治体が中心となって共同のお墓の利用を奨める地域も増えてきました。ご遺骨は、宗教・宗派にかかわらずお墓の運営管理者によって責任持って永代供養されることになります。
ここがポイント
最近では、遺骨をゆうパックで送る「送骨」によって合同墓に納骨したあと永代供養をしてもらえる霊園もあるようです
-

-
遺骨をゆうパックで送る
墓じまいや改葬などを考えている方へお知らせします。遺骨が郵送できるんです! お墓が遠方にあるのでお墓参りができない、このままお墓を残しておくと管理が大変など様々な理由でお墓の管理について悩んでいる方も ...
そこでおすすめなのが
『遺骨相談.com』
手元供養の残りの遺骨の行き先は決められているわけではなく、手元供養にも”こうあるべき”という形はありません。大切なのは、ご遺族や故人の価値観や死生観、そして生き方。亡くなった人を大切にしつつ、遺された人々の想いやライフスタイルなどもふまえて、それらにふさわしい手元供養と残ったご遺骨の行き先を決めるといいでしょう。手元供養の残りの遺骨についてのお悩みや疑問などがありましたら、ぜひお気軽にご相談してください