
今回の墓じまいについての記事は、墓じまい後は新たに墓石は建てずに永代供養塔などに納骨し永代供養をするというものです。墓じまい後、新たに別の土地にお墓を建て納骨する場合とは違うところもあります。
墓じまいとは?
お墓を処分すること。
墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。
法律上、お墓に納められている遺骨を勝手に取り出すことはできませんが、手続きを踏むことで、墓じまいが可能になります。
墓じまいの手順
墓じまいは、家族や親戚に相談し、同意を得てから始めましょう。そして、お墓の管理者に墓じまいの意志を伝えましょう。この時、寺院墓地にお墓がある場合は、離檀料といってお礼の気持ちを形にしてお渡しします。金額は、法事のお布施3回分が妥当です。これまでの法要で、故人1人につきお布施を3万円包んでいたならば、3回分で9万円になりますが、このような場合は、キリの良い10万円を包むのが好ましいです。
お墓の管理者側もこちらも気持ちの良い墓じまいをするために大切なことです。
(1) 墓じまい・改葬の手続き
家族や親族、お墓の管理者の同意を得たら次は、証明書などの手続きです。墓じまいをするということは、遺骨を今の場所から別の場所に動かすということです。これを行うには改葬の手続きが必要になります。
遺骨は勝手に取り出したり、埋めたりすることが禁止されています。
墓じまい時の必要書類
- 受入証明書(新しく納骨する地域の管理者が発行)
- 改葬許可申請書(いま納骨している地域の自治体の役場かHPで発行)
改葬許可申請書に今のお墓の管理者から署名と捺印をもらう - 改葬許可申請書と受入証明書を今のお墓がある自治体に提出し改葬許可証を発行してもらう
- 埋葬証明(今のお墓の管理者が発行)
上記の【受入証明書・改葬許可証・埋葬証明】が揃ったら、現在、納骨している地域の自治体に提出します。そうすることで、改葬許可証が交付され、ここでやっと遺骨を取り出すことができます。
(2) 遺骨を取り出す
遺骨を取り出します。(この時、閉眼法要をする人もいます。)
遺骨を取り出す時も費用が発生します。
(3) 遺骨の安置
取り出した遺骨は、納骨する日まで一旦自宅で安置します。
改葬許可証を紛失しないようにしましょう。
遠方で墓じまいをするという方、公共機関を使ってお骨を持って帰るという方、お骨の入った骨壺は重たいです。持てないことは全くないですが、他の荷物も一緒となると厳しい場合もあると思います。ヤマト運輸や佐川急便といった配送サービスでは取り扱いできませんが、郵便局のゆうパックは、遺骨の郵送もできます。
(4) 納骨
新しい納骨先に納骨します。
納骨先によっては、寺院や霊園の維持管理に充てられるお金である年間管理料が必要になります。
- 手元供養(年間管理料:0円)
- 樹木葬(年間管理料:一般的には0円、数千円かかるところもある)
- 散骨(年間管理料:0円)
- 納骨堂(年間管理料:3,000円~15,000円)
- 一般墓(年間管理料:3,000円~15,000円)
- 永代供養塔(年間管理料:3,000円~15,000円)
墓じまいの費用
以下は、今あるお墓の撤去費用です。それぞれ、おおよその金額です。お墓のある地域によって多少の差はあると思いますが、おおよその相場は、1㎡あたり10万円~12万円、墓石の処分費用は1t当たり3,000円~5,000円といわれています。
- 墓石・区画の処分費用:20万円~50万円(地域や広さによって大きく変わります。)
- 離檀料:10万円~20万円
- 遺骨の取り出し料:3万円
- 閉眼法要:2万円~5万円
墓じまいの正確な費用は、石材店が実際に出向いて現状を見てみないことにはわかりません。相見積もりをすることが一番望ましいですが、霊園や寺院によっては、石材店が指定されていることもあるので、墓じまいの相談をするときに確かめてみましょう。
墓じまいの費用・詳しい内訳
- 石碑解体撤去工事
- 石碑・外柵解体撤去工事
- 基礎解体撤去工事
- 残土処分費
- 石材処分費
- 土地の整地化費
- 重機運搬費
墓じまいをし、別の場所に新たにお墓を建てる場合は、新設するお墓の費用も出てきます。
永代使用料に約50万円~200万円、墓石代に約100万円~200万円、開眼法要に約2万円~5万円。低く見積もっても、新しくお墓を建てるには200万円はかかります。
しかし、お墓を建てなくても供養の仕方は色々あります。
墓じまいをする理由
厚生労働省の平成30年度衛生行政報告例(最新)によると、改葬件数は全国で115,384件です。
墓じまいを考えている人、また墓じまいをすると決定している人には理由があります。家の引越しと違って、お墓の引越しや処分は親戚まで巻き込むことになります。そうまでして、墓じまいをしようするワケは何なのでしょう。
実家にお墓はあるけれど、就職や結婚で地元を離れたことや、ご夫婦二人きりでお墓を承継する人がいないこと、一人っ子同士で結婚し、地方に別々になっている両家のお墓を守っていくのは大変ということ、十人十色で墓じまいをする人には色んな理由があります。
昔はなかった墓じまいという言葉なので、いざ墓終いを実行しようとなると、少し気が重いかもしれません。親戚の反対もあるかもしれません。しかし、年に一度お参りできるかどうかのお墓をそのままにして、いつか無縁墓にしてしまうより、思い切って墓じまいをするほうがいいのかもしれません。
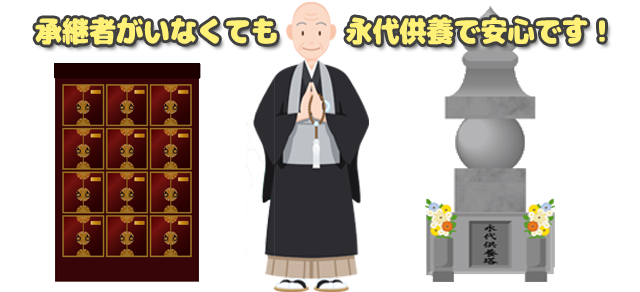
本当の意味での墓じまいは、墓じまいでよくある「お墓を承継できないから墓石を撤去する、そしてお骨は納骨堂に納骨し永代供養をする」ではなく、遺骨を散骨することなのかもしれません。しかし、散骨では、お骨をまいた時点で散ってしまいますから、お参りしたい時に手を合わせることはできません。