

檀家制度
檀家制度とは特定の寺に所属していて、葬祭供養一式を任せる代わりにお布施としてその寺の経済支援を行うことです。
特徴
檀家は個人単位で入るのではなく、家単位で入る事になります!
檀家制度の始まり
檀家制度の起源は、仏教が伝来した飛鳥時代にさかのぼります。
飛鳥時代
仏教が有力者の信仰対象になり、有力氏族が寄付し合って寺院を建立し(建立されたお寺を氏寺と呼ぶ)仏教・諸宗派を保護され、氏寺で自分たちを支援してくれる有力氏族の為に葬祭供養を行ったと言われます
江戸時代
キリスト教が禁止となる。江戸幕府はすべての民衆(身分問わず)に必ずどこかの寺院に所属し、寺院が発行した証明書(寺請証文)を受けることを義務付け、証明書(寺請証文)をもってキリシタンではないことを証明したと言われます。お寺は家の戸籍を管理するなど現在の役所のような役割を果たすようになっていました。これを『寺請制度』と呼んでいました
現在
『寺請制度』を元にしたものを『檀家制度』といい、広く民衆から受け入れられ、民衆が心のよりどころを求め、仏教を信仰し、お寺にお布施、奉仕することで死後極楽往生できると信じられています
このように江戸時代から続く檀家制度ですが、現代では世代交代と共に檀家制度に疑問を持つ人も増えてきており、お寺との関係について考える時期にきているのかもしれませんね
お寺の種類
日本全国にお寺は約77,000件あると言われ、運営方法によって3つに分けることができます。
お寺の運営方法について
- 檀家寺
- 信者寺
- 観光寺
檀家寺
家単位での信仰者(檀家)の葬祭供養一式を行い、檀家専用の墓地を境内に持っていることも多い。檀家からの護寺会費(お寺を守る会費)やお布施などによる運営
役割
先祖供養を行うことで檀家の心を癒し、これからの家族繁栄を願う
信者寺
参拝できるお寺で、祈祷(きとう)や祈願も行っています。境内でおみくじを引いたりお守りなども購入可能。お寺を訪れた人の参拝料や特別な行事(開帳など)の際に募った寄付等による運営。
役割
個人単位で幅広く信仰を募り、今を生きる人の心願成就を願う
観光寺
観光客や修学旅行生が多く訪れるお寺で、お寺を中心に地域一帯が観光地化されていることが多い。主に拝観料での運営。清水寺(京都)や善光寺(長野)などが観光寺にあたります。
役割
受け口を広くとり、素晴らしい仏閣建築物や貴重な仏像から歴史や学びを伝える
お寺と付き合うメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| ・もしものとき(近親者が亡くなった際の葬儀など)に信頼のおける僧侶に来てもらえる
・悩みや不安事があれば相談にのってもらえる |
・檀家になる必要がある |

墓じまいについて
-

-
承継しないお墓を墓じまい、墓じまいの費用は!?
今回の墓じまいについての記事は、墓じまい後は新たに墓石は建てずに永代供養塔などに納骨し永代供養をするというものです。墓じまい後、新たに別の土地にお墓を建て納骨する場合とは違うところもあります。 墓じま ...
新しい供養の仕方
昔と違って核家族化や都心移住等により「家」という意識が薄れてきているのが現状。しかも少子高齢化から供養する後継者がいなくなると、先祖代々の供養に対して不安を持つ人も増え、継承を前提としない「新しい供養のかたち」を選んでいる方も多くなっているとのこと。
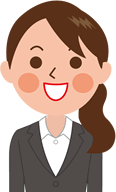
送骨という考え方
送骨とは、手元にある遺骨をゆうパックを利用して寺院に郵送し、寺院が遺骨を供養することをいいます。寺院に到着した遺骨は、永代供養墓に納骨して供養されるので安心してください。「遺骨を郵送するなんて!」と思うかもしれませんが、全国の送骨の件数は年々増加傾向にあります。

供養の仕方も今は様々です。『遺骨相談.com』では収骨後の遺骨を郵送で送ることができます。その後の供養までトータル的にサポートしてくれるのでとても安心です。亡くなった人を大切にしつつ、遺された人々の想いやライフスタイルなどもふまえてふさわしい供養を行うことをおすすめしているようです。遺骨についてのお悩みや疑問などに関して気軽にご相談できるかと思います