お墓は前もって建てるほうがお得なの?
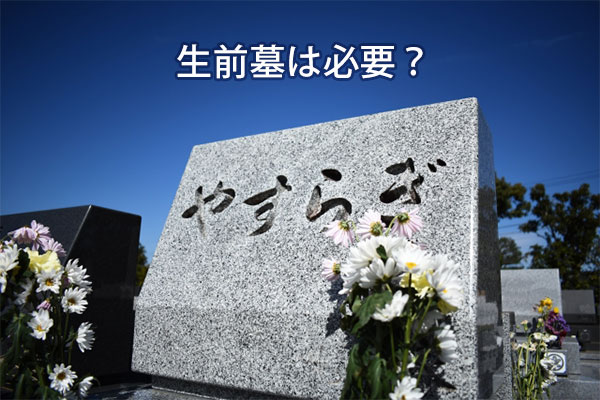
生前にお墓を建てることを寿陵(じゅりょう)といい、長寿を祈願するものなので縁起がいいという考えもあります。
生前にお墓を用意するメリット
- 自分の趣味嗜好が反映できる
- 四十九日後にすぐ納骨できる
- 死後の家族間トラブル回避になる
- 一部の人にとっては相続税対策になる
自分でお墓にこだわることができる
墓地の立地や苑内の雰囲気、墓石の石材の種類やデザイン、樹木葬等埋葬をどのようにするかまで、自分の意思を伝えることができます。
残された家族にとっても、『本人が気に入ったお墓に埋葬してあげられた』というのは慰めになるでしょう。
四十九日までに建てるのはトラブルの元
墓石タイプのお墓を新しく建てる場合、完成までに2ヶ月~2ヶ月半はかかると言われています。
四十九日後にすぐ納骨したくて、故人が亡くなってから1ヶ月半でお墓を建てたいという遺族もいますが、短い期間に焦って建てるとトラブルの元になります。
間に合わせることが目的になってとりあえずのお墓を建ててしまうと、後悔しても後の祭りです。
生前購入なら時間の制約がなく条件にこだわってお墓を選べますし、四十九日後すぐに納骨することもできます。
遺族がお墓のことで奔走しなくてよい
墓地を探し回ったり、お墓を建立する手続きといった慣れない事務手続きは、肉体的・精神的にも負担になります。こうした負担を減らしてあげたいなら、生前購入は有効な手段となります。
また1番にも繋がりがある内容ですが、お墓に関する意見をすり合わせできていると、親族に横やりを入れられても『故人の希望だ』と言って揉めるのを止めることができます。
多くの遺産がある人には節税効果も期待
お墓や仏壇などの祭祀財産は非課税で、相続税の対象ではありません。したがって、お墓を本人が生前に購入していれば、亡くなった後に妻や子供が税金をかけずに引き継ぐことができます。
ただしよほど多くの遺産がある人以外、相続税の基礎控除内におさまるケースが多いので、一概に相続税対策として有効とは言えません。
お墓にお金をかけられなくなってきている現実
そもそも葬儀の時点で家族葬や直葬が増えてきており、年忌法要も十三回忌で弔い上げするなど、年々簡略化してきています。
現代では時間的な余裕がないだけではなく、そもそも葬儀やお墓にお金をかける余裕がないということもあります。
お墓を買わなくても、話し合いはおすすめ
お墓は必ずしも、生前に用意する必要はありません。
一部では遺骨が手元にないとお墓を建立できず、そもそも生前購入はできないというところもあります。
死後のことを相談すると、『縁起でもない』といって嫌がる人もいますが、遺骨をどうするのかの問題は、死後必ず起こります。
お墓がなければなおさら、お互いの考えを確認しておくと、金銭面でも精神面でも安心が得られます。
負担の少ないシンプルな埋葬とは
おススメ
自宅で手元供養した後に合祀墓へ埋葬する
火葬後の遺骨は自宅に安置して手元供養をし、気持ちの整理がついた頃、合祀墓へ埋葬します。
合祀墓(ごうしぼ)は遺骨を骨壺から出した状態で、他の大勢の方と一緒に埋葬してご供養をするお墓です。
遺骨を骨壺から出すと埋葬に必要なスペースが少しで済みますし、墓碑は合祀墓にあらかじめ用意されているものを共有する形になりますので、石碑や樹木を購入する必要もありません。
価格帯も4万円~8万円程度のため、経済的な負担をかなり軽くすることができます。
また合祀墓に納骨する際には、送骨(そうこつ)というサービスを利用することもできます。
ゆうパックを利用して遺骨を霊園に送るため遺骨を抱えて移動する手間もなく、体力に自信のない方や、忙しくなかなか時間を作ることができない方に利用されています。
-

-
送骨(そうこつ)ってどういうもの?
自宅に居ながら遺骨を整理できる『送骨』 送骨とは、配達サービスを利用してお寺や霊園に遺骨を送り、納骨してもらうことを言います。 跡継ぎのあるなしに関わらず、お寺や霊園の墓地管理者がお墓をきれいにして供 ...
今はこのように様々なニーズに対応したサービスがありますので、生前墓は必ずしも必要ありませんが、家族の方と話し合いをしておくことをお勧めいたします。