

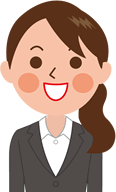
永代供養とは、様々な理由でお墓参りができない人に代わってお寺や霊園の管理者が遺骨を供養・管理してくれるお墓の事です。
-

-
永代供養とは?永代供養墓の種類について
永代供養について 葬儀に出席したことがある人や、実際に自分の身内がなくなったときに、聞いたことがあるかもしれませんが、永代供養ってご存じですか? 永代供養とは 永代供養というのは、「供養の方法」のこと ...
永代供養先が供養してくれるので1周忌はしなくてもよい?
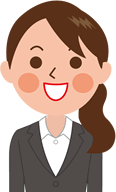
これは、遺族や故人と親しかった方たちが追善供養することで、故人がより極楽往生できるとされているからです。
永代供養のご供養は、寺院や霊園が行ってくれますが、一般的な場合、春と秋のお彼岸やお盆、月命日や回忌供養、合同供養日など永代供養先によって様々です。
永代供養がご供養をしてくれているからといって遺族で1周忌の法要を行っても何の問題もありません。
故人をより丁寧にご供養する意味からも、1周忌は行った方がよいかもしれません。
永代供養での1周忌の手順
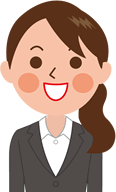
永代供養で1周忌を行う場合の手順はだいだい以下のようになります。
1周忌によぶ人を決める
まずは1周忌に来てもらう人を決めます。
1周忌は家族や親族で行うのが一般的ですが、故人の親しかった友人をよぶケースもあります。
永代供養での1周忌会場の手配をする
呼ぶ人を決めたら、案内所を送ったり、電話などで連絡してします。
1周忌にくる人数が決まったら、会場や会食の手配をします。
1周忌は、主にお寺や自宅、斎場などで行いますが、永代供養先のお寺が遠い場合などは、自宅や斎場などで行います。
お寺や斎場、霊園内の施設などを利用する場合には、予約をしておきましょう。
1周忌後の会食用のレストランなどの手配
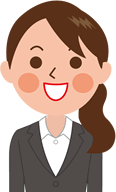
一般的に、斎場で1周忌を行った場合、会食も斎場でする流れになりますが、自宅やお寺で1周忌を行う場合は、レストランなどで会食したり、自宅で会食することも。
事前にレストランなどを予約したり、法事用の仕出しを頼んだりしておきましょう。
永代供養の法要はいつまで?
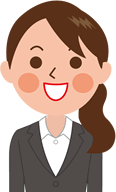
永代供養の場合、初めから供養塔などへ合祀となるタイプと、個別墓タイプ、集合墓タイプなどがありますが、三十三回忌など一定期間が過ぎると合祀されます。
合祀されると、その後の法要は行わないというのが一般的です。
永代供養をするとお寺や霊園が供養してくれるので、法要のことを忘れがちになりますが、節目である法要くらいは個人を偲んでご供養してみるのもよいかもしれません。